大阪控訴審判決は、控訴人との雇用契約を認めない~控訴人は労働者認定
訴外Bらとの雇用契約は成立するのか。
前記アのとおり労働基準法上及び労働契約法上の労働者に該当する酵素人と雇用契約を締結したのは、むしろ訴外B又は訴外Aで有ると介する余地がある
(12ページ下から6行目~)
ということなので、訴外B又は訴外Aとの雇用契約が成立するか否かを検討してみよう。
まず、控訴審判決が示す雇用契約の要件を振り返ってみる。
先ほど引用した少し手前の部分だ(12ページ下から14行目~)
①上記認定判断のとおり、控訴人と被控訴人が倉庫作業開始時点で同作業を業務内容とする雇用契約を締結したとは認められないこと、②控訴人に倉庫作業に従事させるべく働きかけたのは訴外Bらであったこと、③倉庫作業の報酬額を決定したのも訴外Bらであること、④倉庫作業に関して、被控訴人が配置を含む控訴人の具体的な就業態様を一定の限度であっても決定し得る地位に無かったこと
この部分の詳細についてはパナソニックプラズマディスプレイ事件の誤用だと記し、大阪控訴審判決独自の着眼だと述べた。
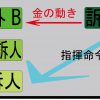
控訴審判決の判示する要件とは、①契約の始期に雇用契約締結の意思があったか否か、②契約を働きかけたのは誰か、③報酬額を決定したのは誰か、④具体的な就業態様を一定の限度であっても決定し得る地位にあったか否か、だろう。
被控訴人には全てが当てはまらないとしているが、訴外Bらには当てはまるのだろうか。
①契約の始期に雇用契約締結の意思は存在したか。
契約の始期に雇用契約締結の意思の存在は、被控訴人を含めて訴外Aにも訴外Bにも無い。そんなものが有れば、各種保険の被保険者資格確認の請求の為に行政の手を借りる必要は無かっただろう。そんなものが無いからこそ、本事件提訴までに約2年の月日を要しているのだ。
②契約を働きかけたのは誰か。
契約を働きかけたのは、たしかに訴外Bとすることも不可能では無い、しかし訴外B代表者の尋問では、被控訴人と相談するようにと控訴人に促し、訴外B自らも被控訴人と話し合いの場を持ち、何らかの合意を得てることになる。つまり被控訴人には訴外Bからの申出に合意しない、何かしらの契約を締結しない選択があった事を否定できない。いや、何ら資本関係すら無い被控訴人と訴外Bとの間で本事件の契約を、被控訴人が断れなかった理由が思い浮かばない。
③報酬額を決定したのは誰か。
報酬額を決定したのは、被控訴人が訴外Bに打診したことから、訴外Bが決定したと判断しているようだが、訴外Bは被控訴人から打診のあった時に、訴外Aに打診していなかった証拠はない。つまりは訴外Bが訴外Aに打診していた可能性は残ったままだ。控訴審判決の言葉を借りるのなら訴外Bが訴外Aに打診した余地がある。
④具体的な就業態様とはなんだ。
最後に、「具体的な就業態様に一定の限度で決定し得る地位」を控訴審判決は何ら具体的に記していないが、訴外Bは被控訴人との間に締結された何らかの契約を解除する事で、控訴人を倉庫へ行かせないようにした、同じ事は訴外Aにも言え、訴外Bとの間の何らかの契約を解除すれば控訴人が倉庫に行かせないようにする事が可能だ。いずれも控訴人との直接の関係ではない事から何ら決定し得る地位とは考えられない。
関係各社のどことも雇用契約が成立しない。
いずれも要件には当てはまらない。
訴外Aも、訴外Bも、控訴審判決の示す、要件に当てはまらない事になってしまう。控訴審判決は訴外Bらと示唆するが、上記の通り、訴外Aや、被控訴人との間に雇用契約が発生し得る余地がある。訴外Aから見ると②の契約を働きかけたことに該当しないから、なおさら訴外Aと控訴人との契約は雇用に限らず有り得ない。
訴外Aの立場で考え得るのは、就業場所の提供や具体的な業務内容の指示・指導と労働時間の管理くらいだろう。つまりは労働者派遣における派遣先の為し得る範囲に限られる。
元々が異常な法律関係なのだから、どこかに軸を定めないと、浮遊してしまう。理由や目的は解らないが、本事件を棄却する為だけならば、控訴人と被控訴人の関係だけに着目すれば良いのかもしれない。まあ、それすらも、曖昧で軸の無い論理だと繰り返し述べているが、他者である訴外Aや訴外Bとの関係すら明確にならない、いや把握していない、理解していないとしか思えないのが、本事件の大阪高裁控訴審判決だ。
大阪高裁の迷走~各社共に雇用契約が成立する(しない)余地がある。
上記でリンクを張った、前回の記事を振り返ってみよう。
平成21年最判(パナソニックプラズマディスプレイ事件)では、控訴審判決が要件とする「①契約の始期の雇用契約締結の意思」がない。この①が大阪高裁独自の論理であり、本事件の特殊性なのだろう。
パナソニックプラズマディスプレイ事件では、もともとが雇用契約による労働者派遣が前提になっている事に当事者間に争いは無いからだ。厳密には、そこが原告の最たる争点であり派遣先との雇用契約の成立を争点としているのだが、同事件当時の当初は同事件の業務では労働者派遣が認められてなかったのだから、全体として当事者関係が労働者派遣なのか否かで、高裁と最高裁で分かれた判示となっている。
最高裁は、仮に法が整備されていなかったとしても、労働者派遣の外形を装う以上、例え違法で歪で有ったとしても、労働者派遣とみなすものとして同法が適用されると判示している。
また、同事件では、原告の労働者が、派遣先において、左遷とも思わしき部署に異動になっているが、実態を推認すれば、その為に新しい部署を作ったと思わしきものであり、または違法な労働者派遣の状態を是正する為の派遣先の都合であるのだから、移動の発端は派遣先の意向によるものに他ならないのではないのだろうか。しかし最高裁は派遣元に、本事件の訴審判決の判事の言う「④具体的な就業態様に一定の限度で決定し得る地位」が有ったと言う。
つまり「具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位」とは何なのか、そこを掘り下げ、具体的に、明確に、されるべきだろう。
もっと言えば外形上、例え違法でも労働者派が就業態様の前提となる以上、派遣先との雇用契約が生じる事は限りなく薄い可能性だと考えている。この事を受けて労働者派遣法の平成24年改正(労働契約見なし制度は平成27年施行)が立法されてのではないのだろうか。
本事件においては、倉庫業務の対価を支払っていたのは被控訴人であり、労働者が労働の対償として受領する金員は賃金(労基法11条)であり、賃金は使用者が直接支払わなければならない(労基法24条)事。また、控訴人に対して、「倉庫に行かなくて良い」と指示したのは被控訴人である事等、訴外Bらを使用者と考えたとしても矛盾が生じてきて、「被控訴人が使用者であるとする余地がある。」そんな理屈が通ってしまう事になってしまう。

